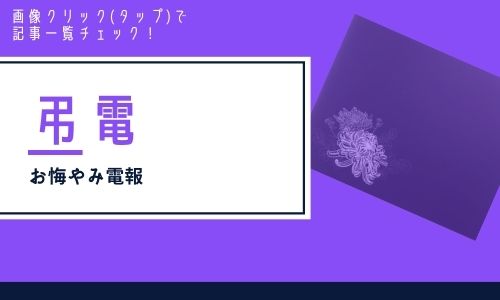お香典を準備して通夜・告別式に参列しますが、お香典を渡すだけでもマナーがあります。
間違えた方法で渡せば、もしかしたら不快な思いをさせていた、なんてことにも…
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 香典の受け取りを辞退されたら
- お香典を渡すタイミング
- お香典を渡すときのマナー
お葬式で恥をかかない、香典を渡すときのマナーとタイミングを解説します。
香典袋の書き方や香典の金額の相場を紹介した記事もあります。
↓ ↓ ↓
香典袋の種類と書き方のマナーと相場
あわせてチェックしてみてください。
お香典を渡すときのタイミング
お香典の歴史は古く、食料を送ってお坊さんや参列者の食事にしていたことが始まりです。
突然の不幸による遺族の負担、これを軽減させる相互扶助の目的でお香典を渡します。
霊前に供える香や線香の代わりに、現在では現金を包むのが主流です。
故人や遺族と関係が深いほど包む金額は多くなって、故人の親族となればそれなりの金額を包みます。
お香典を渡すタイミングは、お通夜か告別式のどちらに参加するかで違います。
お通夜と告別式への参加割合
全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)が実施したアンケート調査の結果があります。
それによると、お通夜と告別式への参加割合は、お通夜のほうが多いというデータがあります。
| 参列者(人) | |
|---|---|
| お通夜 | 3,342 |
| 両方 | 2,853 |
| 告別式 | 1,230 |
結果的に、⓵お通夜に参列、⓶お通夜と告別式に参列、⓷告別式に参列の順で多いのが分かります。
マナーの観点からいえば、普段づきあいの親しい間柄なら、通夜も告別式も参列します。
一般参列者は、できるだけ告別式に参列するようにしますが、事情があって告別式に参列できなければ通夜でも構いません。
受付のタイミングで手渡す
お香典は、通夜か告別式に受付の人に手渡します。
通夜と告別式のどちらにも参列する場合、通夜の受付で渡すのが一般的です。
| 持参数(人) | |
|---|---|
| お通夜 | 5,418 |
| 告別式 | 2,007 |
ですがマナー上は、告別式に参列したときに渡すことをおすすめします。
2回に分けて渡すのは、不幸が重なるという意味からマナー違反になります。
通夜は18時か22時ころに行われるのが一般的ですが、お坊さんが読経している間に参列し、焼香がすめばすぐに引き上げます。
お香典を渡すときのマナーや挨拶
それでは、お香典を渡すときのマナーについて説明します。
香典を包む袱紗(ふくさ)とは
香典を手渡す前に「袱紗」に包んでおきます。

袱紗に包むのは、香典袋(不祝儀袋)が汚れたり折れ目がつかないようにするためです。
手渡す際のマナーになりますが、どうしても用意できない場合はハンカチなどで代用できます。
袱紗を持っていないのであれば、高価なものではないので、いざという時のためにも用意しておきたいところです。
袱紗(ふくさ)の包み方
袱紗の包み方はとても簡単です。
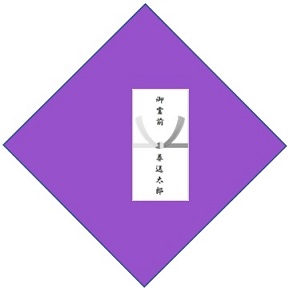
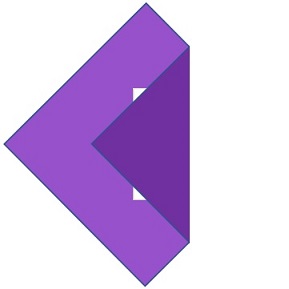

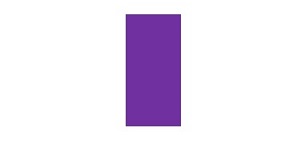
不安があれば、1分程度の動画で詳しくお香典の包み方を確認してください。
出典:小さなお葬式
香典を手渡すときの挨拶
いざ受付でお香典を渡すとき、無言では失礼になります。
袱紗からお香典を取り出し、受付の人に渡すときには簡単にお悔やみの言葉を添えます。
- 渡すときに、袱紗の上にお香典が乗るように開く。
- お香典を両手で持つ。
- 相手に表書きの文字が向くように差し出す。
渡すときの挨拶は、「この度は、まことにご愁傷様です」や「心よりお悔やみ申し上げます」で大丈夫です。
お悔やみの気持ちを表すために、小声で語尾は分かりにくいほうがマナーとして合っています。

香典を渡したら、名簿に住所氏名を記入します。
故人の親族が受付でお香典を渡す場合、先ほどの挨拶では違和感が残ります。
受付をしてくれる人は一般的に、町内会の人や、遺族の会社関係者になるので、親族の場合は受付の人に親族であることを伝えます。
渡すときの挨拶は、「お世話になります。親族のものですが、受付をお願いします」などと言いましょう。
受付が無い場合に香典をどうするか
受付がなければ、遺族に直接渡すか、ご霊前に供えるようになります。
遺族に直接手渡すなら、先ほどの受付での渡し方と同じです。
手渡すときのお香典の向きと、お悔やみの言葉を忘れないように注意してください。
ご霊前に供えるなら、焼香したあとに祭壇のお供えに置きますが、向きは受付のときと反対になります。
お香典は亡くなった方に手向けるものではなく、遺族への相互扶助が目的なので、その向きは自分側になります。
通夜ぶるまいの席に呼ばれたら
通夜ぶるまいとは、通夜のあとに、お坊さんや親族と身近な人をねぎらうための席です。
本来は親しい人のために、葬家の好意でお酒や軽食が出されます。
もし葬家に通夜ぶるまいの席に勧められたら、もてなしを受け、早々に切り上げるのがマナーです。
間違っても、その席で酔いすぎたり、大声や笑い声などは出さず、故人の思い出を語るくらいにしましょう。
香典の受け取りを辞退されたら

喪主が香典の受けとりを辞退することは、それほど珍しいものではありません。
2014年のデータでは、受けとりを辞退した割合は28.4%というデータもあります。
近年は、家族葬の割合も増えてきているので、香典を受けとらないという人も増えています。
故人や喪主の意向なので、尊重して香典はやめておきましょう。
どうしてもという場合は、お葬式に参列できないときと同様、香典の代わりに弔電や供花を送ります。
以上、お葬式で香典を渡すときのマナーとタイミングを説明しました。
お香典は袱紗に包み、渡すときに取り出します。
その際は、きちんと挨拶の言葉を添えるようにしてください。
あとは、お香典を渡す向きに注意すれば、そこまで難しいことはありません。