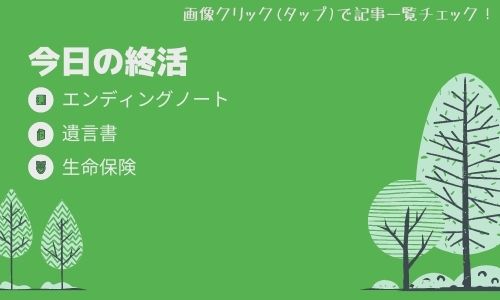遺言を書いておく最大のメリットは、もしものときに残された家族が悩まなくてすむことにあります。
遺言を残すことで家族にあなたの意思を伝えたり、相続の手続きにおいて無用な時間や親族のトラブルを減らせます。
しかし遺言書の作成方法にミスがあれば、いざという時にその機能を果たせないばかりか、無効な遺言書がもとで不要な遺族間のトラブルにも…
このページを最後まで読めば、次のことがわかります。
- 法的に効力のある遺言書にできること
- 相続問題にならないために
- 効力のある遺言書の作成方法
無効な遺言書と効力のある遺言書のちがい、遺言の方式の種類別のメリット・デメリットを説明します。
法的に効力のある遺言書にできること
あなたにもしもの事があったとしましょう。
そのとき残された家族は、悲しみでしばらく正常な判断ができなくなります。

しかし時間の経過とともに気持ちは落ち着き、そして現実に戻されたとき、つぎの問題に直面します。
- 生活費をどうすればいいのか。
- 自動車や不動産をどのように分配するのか。
- 遺品をどう扱えばいいのか。
それらの問題を解決し、スムーズに相続を終わらせるためには、法的に効力のある遺言書が必要になります。
民法の要件を守って適正に作成された遺言書は、法的に強い効力をもちます。
遺言書の効力は絶大
遺言書がなければ、遺産の分配方法は法定相続人の話しあいで決め、遺産分割協議書を作成することで分配されます。
仮に、遺産分割協議が終わったあとに遺言書が見つかれば、協議結果が無効になることもあります。
遺言書の効力は大きなものですが、それだけに後で見つかれば、余計なトラブルの種にもなってしまいます。
これから遺言書を作成するなら、エンディングノートに保管場所を書くことをおすすめします。
遺言書では他人に遺贈もできる
遺言書に指定があれば、法定相続人以外に遺産を譲ることもできます。
fa-arrow-circle-right法定相続人って何?
また、一部の相続人を指定して、ほかの相続人より多く遺産を分けることもできます。
例えば長男に5,000万円、次男に1,000万円なんてことも、遺言書で指定すれば可能になります。
このように、特定の相続人や相続人以外に遺産の分割を指定して譲ることを遺贈といいます。
遺贈するなら、法定相続人が最低限の遺産を受けとる権利である遺留分には注意しておきましょう。
fa-arrow-circle-right遺留分って何?
効力のある遺言書を無効にする行動とは
遺言書は民法で決まりがあって、それを守られなければ、どれだけ良い内容でも遺言書として無効になります。
逆に決まりさえ守って作成すれば、効力のある遺言書として認められます。

効力のある遺言書を無効にする行動について説明します。
遺言執行者の指定していない
遺言の内容をスムーズに実現するためには、遺言執行者を遺言書で指定します。
遺言執行者は相続人の利益のためではなく、故人の意思を実現するため、強い権限が民法によって与えられています。
遺言執行者を指定しなくても遺言書としては有効ですが、相続人が遺言の内容を守ってくれないこともあります。
そんなときに遺言執行者が、相続人の勝手な行動から遺産を守ってくれます。
遺言書の作成方法を守っていない
遺言書は法的に効力が守られますが、作成の要件にミスがあれば、遺言書として無効になってしまいます。
「遺言書としては無効かもしれないが、遺言書の通りに相続しろ」
「遺言書が無効なら法定相続分で分配する」
このように要らぬトラブルとならないように、決められた作成方法は守りましょう。
fa-arrow-circle-right自筆証書遺言の作成方法
fa-arrow-circle-right秘密証書遺言の作成方法
遺言を残せる年齢に達していない
15歳になれば誰でも遺言を残せることが、民法961条で決まっています。
未成年だからといって、親が勝手に遺言書の内容を無効にはできません。
もし、15歳になっていないなら遺言書は無効になってしまいます。
証人の条件を守っていない
公正証書遺言と秘密証書遺言を有効な遺言書にするためには、公証人と証人2人の証明が必要です。
公証人は、裁判官・検察官・弁護士などの法律に従事する人から法務大臣が任命した人です。
一方で、証人になってはいけない人の条件は緩めです↓
- 未成年者
- 証人、証人の家族が遺産相続する立場
- 公証人の親族、書記や使用人
ですが何かの手違いで、この証人になれない条件に当てはまれば、遺言書が無効になってしまいます。
知人などに依頼するなら、証人の条件に注意しましょう。
後見人の有利になる内容を書いている
認知症の人や、未成年の子供など、その人に代わって財産管理や契約などの法律行為をする人を後見人といいます。
被後見人(ここでいう認知症の人や、未成年の子供)が遺言書を作成するときの条件です。
- 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
- 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。
もし後見人や後見人の家族の利益となる内容が書かれていれば、遺言書は無効です。
ただし、後見人と被後見人が家族であれば、遺言書として効力はあります。
成年被後見人の遺言に医師が立ち会っていない
法律行為の判断ができない人、例えば認知症・精神障害・知的障害などの状態の人を成年被後見人といいます。
その状態の人が、一時的に判断能力を回復させることがあります。
判断能力が一時的に回復したときに、遺言書を残すことができますが、医師2人以上の立会いが必要です。
- 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
- 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。
ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。
立ち会った医師は、遺言するときに判断能力があったことを遺言書に書き、署名と押印しなくては無効になります。
遺言書1式に遺言者2人分ある
民法第975条で「遺言は2人以上が同一の証書ですることができない」とされています。
夫婦や親子でまとめて1つの遺言書を作成しようとしても無効でなので、必ず別々の証書で作成しましょう。
法的に効力のある遺言書は3種類
法的に効力のある遺言書は、つぎの3種類の方式があり、それぞれ民法で決められた作成要件があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自分で気軽に作成できて、2020年7月から法務局で保管してくれる自筆証書遺言。
fa-arrow-circle-right自筆証書遺言の書き方と見本、法務局に遺言書を保管するメリット
絶対に無効にしてくない人におすすめな公正証書遺言については、このあと紹介します。
誰にも遺言書の内容を知られたくないなら、秘密証書遺言で作成します。
fa-arrow-circle-right秘密証書遺言の検認とメリット・デメリット&手数料
法的に無効になりにくい公正証書遺言
3種類の遺言書の方式のうち、公正証書遺言は公証人と証人が、あなたと一緒に遺言書を作成する方法です。
どのような遺言にしたいか公証人に伝えることで、正確な遺言書を作成してくれます。
公正証書遺言については、民法969条で、次のように決まっています。
- 証人2人以上の立会いがあること。
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
- 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
- 遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認したあと、各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 - 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
自宅や病院や老人ホームなどに、公証人に出張してもらうこともできます。
公正証書遺言のメリット・デメリット
公正証書遺言のメリットです。
- 遺族が家庭裁判所に検認を申請する手間が不要。
- 内容や様式の不備、偽造や変造のおそれがない。
- 原本は交渉役場で適切に保管される。
- 交付された遺言書を紛失した場合、申請すれば再交付できる。
公正証書遺言のデメリットです。
- 公証人への依頼手数料がかかる。
- 証人の立会いが必要。
- 何点か書類の準備が必要。
作成した公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、偽造や変造される心配はありません。
公証人への依頼手数料
公証人へ依頼し、正確な遺言書を作成してもらうわけですから、それ相応の手数料は発生します。
| <遺産の価額> | <手数料> |
|---|---|
| 100万円まで | 5,000円 |
| 200万円まで | 7,000円 |
| 500万円まで | 11,000円 |
| 1,000万円まで | 17,000円 |
| 3,000万円まで | 23,000円 |
| 5,000万円まで | 29,000円 |
| 1億円まで | 43,000円 |
例えば、妻1人だけに7,000万円相続させるなら43,000円の手数料です。
しかし妻3,500万円と息子3,500万円の場合では、29,000円が2人分で58,000円の手数料となります。
公証人に出張してもらう場合には、手数料に50%加算され、公証人の日当と交通費が別途かかります。
また、財産の総額が1億円未満の場合は、手数料に11,000円加算されます。
- 遺言者の身分証(運転免許証、印鑑証明書など)
- 遺言者と相続人の続柄が記載されている戸籍謄本
- 相続人以外であればその方の住民票(法人ならば資格証明書)
- 不動産関係(固定資産税の納税通知書か固定資産評価証明書、登記簿謄本)
- 預貯金(通帳コピー、預貯金額がわかるもの)
遺言書について不安があれば、税理士や行政書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
緊急時に効力のある遺言
じつは民法967条によって、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類以外にも、「特別な方式」が認められるケースがあります。
つぎの項目に当てはまる状況のときは、遺言として認められます。
- 死亡の危急に迫った者の遺言
※証人3人以上の立会いで、その中の1人に遺言の趣旨を聞いてもらいます。それを聞いた人は筆記し、遺言者やほかの証人にその内容を確認、各証人がその筆記の正確なことを承認し、署名押印することで有効になります。 - 伝染病隔離者の遺言
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる人は、警察官1人と証人1人以上の立会いをもって遺言書を作れます。 - 在船者の遺言
船舶中にいる人は、船長か事務員1人と証人2人以上の立会いをもって遺言書を作れます。 - 船舶遭難者の遺言
船舶が遭難した場合において、当該船舶中で死亡の危急に迫った人は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言とできます。
これらの状況に置かれた人は、通常の遺言書を作成しなくても遺言をのこせます。
ですが基本は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類の方式で遺言書を作成しなくてはいけません。